- ホーム
- 岩井事務所だより
岩井事務所だより
- 岩井事務所だより 2016/11/30 【岩井事務所だより】12月号「平成28年分 年末調整のポイント」
- 法人税 2016/11/11 【法人税】中小企業の賃上げ減税(所得拡大促進税制)拡大へ①
- 所得税 2016/11/25 【所得税】配偶者控除見直し③ 減税枠201万円に拡大
- 2016/11/16 【所得税】配偶者控除見直し② 150万円案有力
- 2016/11/08 【所得税】配偶者控除見直し① 103万円超引き上げを明記
- 社会保険 2016/11/28 【社会保険】年金改革法案 与党強行採決
- 2016/11/21 【社会保険】現役並み所得者 介護保険3割負担 平成30年8月から
- 2016/11/18 【社会保険】無年金救済法案成立へ 加入期間10年に短縮②
- 2016/11/14 【社会保険】来年度より介護保険料「総報酬割」へ移行
- その他 2016/11/22 【酒税】ビール税一本化明記
【岩井事務所だより】12月号「平成28年分 年末調整のポイント」
2016/11/30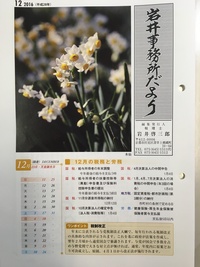
岩井事務所だより12月号は「平成28年分 年末調整のポイント」です。
年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
◎ 平成二十八年分の留意点
⑴ 通勤手当の非課税限度額
平成二十八年一月一日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が月額十万円から十五万円に引き上げられました。
平成二十八年四月の非課税限度額改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要があります。
既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告で精算することになります。
⑵ マイナンバーの収集登録
今年の年末調整はマイナンバー対応が必要です。平成二十八年分の源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりません。
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と身元確認が必要とされています。
本人確認は、原則として、
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で行います。
ただし、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できるときは身元確認のための書類の提示は不要とすることも認められています。
※従業員の扶養家族については、従業員が事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
【法人税】中小企業の賃上げ減税(所得拡大促進税制)拡大へ①
2016/11/11政府は平成29年度の税制改正で、賃上げを実施した中小企業を対象に法人税の減税額を引き上げる方針を固めました。
大企業に比べて遅れている中小企業の賃上げを税制面から後押しして国内の消費を底上げし、経済の好循環につなげる狙いです。
拡充するのは、平成25年度に導入された「所得拡大促進税制」で、現在は企業が一定程度、従業員らへの給与支給総額を増やした場合、その増加分の10%の金額を法人税から差し引けます。
これを、資本金1億円以下の中小企業を対象に、増加分の20%まで引き上げることを目指すとのことです。
「所得拡大促進税制」は事前の届け出が不要で、とても使いやすい制度です。
この給与支給総額には、賞与も含みますので、基本給の引き上げに抵抗がある会社でも活用できます。
今後の中小企業の賃上げが期待できそうです。
ただし、「所得拡大促進税制」は、当初申告要件のため遡りで更正の請求はできませんので、確定申告の際には適用をお忘れなく。
【所得税】配偶者控除見直し③ 減税枠201万円に拡大
2016/11/25政府・与党は24日、平成29年度税制改正の焦点となっている所得税の配偶者控除の見直しについて、控除対象となる配偶者の年収上限を現在の「103万円」から「150万円」に引き上げる方向で最終調整に入りました。
ただ、年収が150万円を超えても、世帯の手取りが急に減らないよう、年収201万円までは控除額を段階的に縮小する配偶者特別控除も併せて導入するとのことです。
また、対象世帯の拡大による税収減を防ぐため、世帯主の所得が900万円(年収1120万円)を超えた場合は制度の対象外とする方針です。
配偶者控除もようやく本決まりになりそうです。
150万円の配偶者控除と201万円の配偶者特別控除の改正で、税務上のパート勤務の壁は解消できるかと思います。
この他にパート勤務の壁として残されているのは、企業の配偶者手当と社会保険の適用要件130万円(大企業は106万円)です。
これらを解決しないことには、パートの勤労意欲を刺激することはなかなか難しいです。
【所得税】配偶者控除見直し② 150万円案有力
2016/11/16政府税制調査会は14日、配偶者控除の見直しを中心とする所得税改革の中間報告をまとめました。
主にパートの主婦の就労を促進するため、妻の年収要件を現行の103万円以下から引き上げる案を初めて明記し、平成29年度税制改正はこの案を基に制度設計を詰める方針です。
今後、与党は配偶者控除見直しの議論で、妻の年収要件を150万円以下に引き上げる案を軸に調整を進めます。
また、対象を絞るために夫の合計所得金額が1000万円(年収換算で1220万円)超の世帯への控除適用を制限する案も検討するようです。
ほぼ原案どおりで中間報告はまとめられました。
配偶者控除の妻の年収要件は150万円案が有力のようです。
このほかに、130万円案も候補に挙がっています。
結局、年収要件の落としどころがどこになるのかが気になるところです。
【所得税】配偶者控除見直し① 103万円超引き上げを明記
2016/11/08政府税制調査会の中間報告原案が7日判明しました。
配偶者控除の見直しで、配偶者の年収要件を現行の103万円以下から引き上げる拡充案を初めて明記しました。
同時に「税収中立の堅持」を掲げ、世帯主を対象にした所得制限を導入して適用世帯が広がりすぎないようにすることで、税収減を避ける必要性も強調しています。
今回の中間案で、「夫婦控除」への転換は財源確保の問題があるとして否定されていますので、採用されることはなさそうです。
目新しい内容としては、配偶者控除の見直しと合わせて、企業の配偶者手当も抜本的に見直すようにと訴えていることです。
税務上は、配偶者控除の他に、配偶者特別控除がありますので、収入と手取りの逆転現象は解消されています。
しかしながら、実際上は、配偶者控除が適用されなくなると企業の配偶者手当も打ち切られることが多いので、上記の問題が解決していませんでした。
今回の言及によってこの問題が解決するかもしれません。
【社会保険】年金改革法案 与党強行採決
2016/11/28与党は衆院厚生労働委員会で25日、賃金の下落に合わせて年金支給額の引き下げを強化する年金制度改革法案を可決しました。
29日にも衆院を通過させる見込みです。
法案のポイントは以下の通りです。
・年金支給額を抑制する仕組みを強化
・従業員500人以下の企業でも労使が合意すれば、厚生年金の加入対象を拡大
・国民年金に加入する女性の出産前後の保険料納付を免除
・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に経営委員会を新設、合議制にする。
野党が「年金カット法案が強行採決された」と訴えて話題となっています。
賃金が下がって物価が上がった場合にも年金がカットされるという内容は確かに厳しいですが、過去にデフレ時にも年金支給額を据え置いていたという経緯もありますので、どこかのタイミングでカットせざるを得ない状況かと思います。
【社会保険】現役並み所得者 介護保険3割負担 平成30年8月から
2016/11/21厚生労働省は18日、現役並みに所得の高い高齢者を対象に、平成30年8月から介護保険サービス利用時の自己負担を現在の2割から3割に増やす方針を固めました。
来年の通常国会に関連法の改正を目指します。
介護保険の利用者負担は原則1割で、昨年8月から一定以上の所得(単身で年金収入だけの場合年収280万円以上)がある人は2割になっています。
厚生労働省はこのうち年収370万円以上などの人を3割にしたい考えのようです。
安倍首相も医療費削減を指示していますので、これは避けられない流れではないでしょうか。
しかしながら、医療制度も税制度もそうですが、国民の批判をかわすために高所得者を狙い撃ちにしている節があります。
今後の安倍政権の支持率の変化も気になるところです。
【社会保険】無年金救済法案成立へ 加入期間10年に短縮②
2016/11/18年金を受け取れない人を減らすため、年金の受給に必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
基礎年金の受給額は、保険料の納付期間が25年間で月額約4万円、10年間で月額約1万6000円となるそうです。
現在の生活保護の金額が月額約10万円前後になることもありますので、これまで働いて掛けてきた年金の金額のほうが低いのは不公平感が残ります。
今後は生活保護の仕組みにもてこ入れが必要でしょう。
【社会保険】来年度より介護保険料「総報酬割」へ移行
2016/11/14政府は11日、40歳〜64歳が支払う介護保険料の計算方法を見直し、収入に応じた「総報酬割」の仕組みに移行する時期を来年度からとする方針を固めました。
健康保険組合などが負担する金額の3分の1について、新しい方法を導入する予定です。
現在は健康保険組合などの加入者数に応じた「加入者割」で計算しており、所得が低い中小企業の社員の負担が相対的に重くなっていますが、この「総報酬割」の仕組みにより、大企業の社員は負担が増える一方、中小企業の負担が減ることになります。
介護保険料を含む社会保険料の半額は企業が負担していますので、介護保険料の負担が減る中小企業にとっては朗報です。
また、中小企業が多く加入する協会けんぽも、介護保険料の負担が減ることにより、国から投入される税金も減ることになります。
今後は、この浮いた財源の使い道も気になるところです。
【酒税】ビール税一本化明記
2016/11/22政府は20日、ビール、発泡酒、第三のビールで異なる酒税の税率を一本化するため、平成29年度税制改正大綱に税率の変更時期と移行期間を明記する方向で調整に入りました。
まず、平成30年度に税区分の根拠となっているビールの定義を緩和します。
その後、メーカーに配慮して最初の税率変更は平成32年10月とし、平成38年10月までに3回に分けて段階的に移行することを検討しています。
この一本化で税率の高いビールは減税となりますが、発泡酒や第三のビールは増税となります。
発泡酒と第三のビールは税率が低く低価格で販売できるため開発されたにもかかわらず、一本化されてしまうとその存在意義が失われてしまいます。
これまでの企業努力が水の泡となってしまうことになり、今後の競争力に影響が出てくるのではないでしょうか。
お問い合わせはこちら

- 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・
- 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・
- 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・
- セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・
- 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・
お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。
 〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
☎ 075-645-1511 FAX 075-645-1512
営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)







