- ホーム
- 岩井事務所だより
岩井事務所だより
- 岩井事務所だより 2016/12/29 【岩井事務所だより】1月号「各種法定調書の作成」
- 法人税 2016/12/05 【法人税】中小企業の賃上げ減税(所得拡大促進税制)拡大へ②
- 所得税 2016/12/09 【所得税・法人税・その他】平成29年度税制改正大綱 与党決定
- 2016/12/06 【所得税】配偶者控除・ビール税 与党税制協議合意
- 相続税 2016/12/22 【相続税】預貯金も遺産分割可能に
- 社会保険 2016/12/02 【社会保険】高齢者医療保険制度 軽減特例廃止により負担増
- 労務 2016/12/28 【労務】違法残業「月100時間超」から「月80時間超」へ引き下げ
- 2016/12/20 【労務】「非正規労働者に通勤費」明記
- その他 2016/12/12 【マイナンバー】スマホ認証で本人確認
【岩井事務所だより】1月号「各種法定調書の作成」
2016/12/29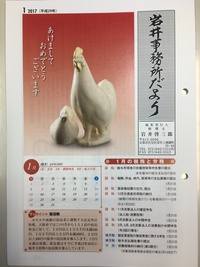
岩井事務所だより1月号は「各種法定調書の作成」です。
毎年一月になると、源泉徴収票や各種支払調書の作成・交付・税務署への提出、給与支払報告書の各市町村への送付等、他の月にはない業務が多くなります。
加えて本年からマイナンバーの記載が始まるため実務処理の負担も増え、様式のサイズが変更されたものもあります。
そこで、これら一月固有の業務のポイントについて整理してみます。
Ⅰ 法定調書
法定調書には多くの種類がありますが、そのうち一般的なものについてポイントを整理すると次のようになります。これらは、一月末までに所轄税務署長に提出する必要があります。
1 給与所得の源泉徴収票
【税務署提出を要する範囲】
・年末調整をした者
(1)法人(人格のない社団等を含みます)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者)及び現に役員をしていなくても平成28年中に役員であった者
平成28年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
(2)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等(所得税法第204条第1項第2号に規定する者)
平成28年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3)上記(1)及び(2)以外の者
平成28年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
・年末調整をしなかった者
(4)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者
イ.平成28年中に退職した者、災害により被害を受けたため、平成28年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた者
平成28年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。ただし、法人の役員の場合には50万円を超えるもの
ロ.平成28年中に主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった者
全部
(5)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等)
平成28年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
なお、「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」は、提出範囲にかかわらず、すべての受給者について作成の上、一月末日までにそれぞれの受給者に交付することになっています。なお、受給者交付用へのマイナンバー記載はしません。
また、給与支払報告書と同時に作成できるように、四枚又は三枚複写となっています。
2 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
【税務署提出を要する範囲】
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲は、平成二十八年中に支払が確定した退職手当等の受給者が、法人(人格のない社団等を含みます)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等)であった者です。
なお、「退職所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後一か月以内にすべての受給者に交付することになっています。
3 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
【税務署提出を要する範囲】
平成二十八年中に講演料や外交員報酬など所得税法第二〇四条第一項等に規定する報酬・料金等を支払った者は、同一人に対する支払金額の合計が一定額を超える場合に提出します。
4 不動産の使用料等の支払調書
(1)提出義務者
平成二十八年中に不動産、不動産の上に存する権利、総トン数二〇トン以上の船舶・航空機の借受けの対価等を支払った法人や不動産業者である個人。
(2)支払調書の提出範囲
同一人に対する平成二十八年中の支払金額の合計が一五万円を超えるもの。
なお、法人に支払われる不動産の使用料等については、地上権、不動産等の賃借権、その他土地の上に存する権利の設定による対価がない場合には、提出は不要です(主に個人の不動産所得のチェックに使われるためです)。
Ⅱ 給与支払報告書
給与支払事業者は、住民税の特別徴収の資料とするために、一月末日までに受給者の一月一日現在居住する市町村長宛に「給与支払報告書」(源泉徴収票と複写で書けるもの二枚)と総括表を提出する必要があります。
【法人税】中小企業の賃上げ減税(所得拡大促進税制)拡大へ②
2016/12/05政府・与党は1日、賃上げした企業の法人税を減額する「所得拡大促進税制」について、平成29年度から中小企業を対象に拡充する方針を固めました。
従業員の平均給与の前年度比2%以上の賃上げを条件に、法人税額から控除する割合を現行の賃上げ総額の10%から22%とする方向で調整しているとのことです。
12月8日にまとめる税制改正大綱に盛り込む予定です。
所得拡大促進税制は、従業員1人当たりの平均給与が前年度を上回るなどの条件を満たせば、賃上げ総額の一部を法人税額から控除する仕組みです。
賃上げ率が2%に満たなかった場合、中小企業は現在と同じ10%分を控除する一方、大企業は対象から外されます。
「所得拡大促進税制」は以前にもお伝えさせていただきましたが、事前の届け出も不要でとても使いやすい制度です。
それが2倍強の控除額に改正されますので、中小企業には賃上げに踏み切る動機となる心強い制度となりそうです。
【所得税・法人税・その他】平成29年度税制改正大綱 与党決定
2016/12/09政府与党は8日、平成29年度の税制改正大綱を決定しました。
主な内容は以下の通りです。
・消費税10%は平成31年10月から。
・配偶者控除の年収要件を「150万円以下」へ引き上げ。ただし、年収1120万円超の世帯主に所得制限。
・ビール類の税率を平成38年10月に全て統一。
・エコカー減税を2年延長。ただし、燃費基準を厳しくして現在の新車の9割から段階的に7割へ絞り込み。
・高さ60メートル超のマンションを対象に固定資産税を高層階は増税、低層階は減税。1階と40階で10%差。
・NISAに非課税期間20年、投資額上限年40万円とする長期積立枠を新設。
・2%以上賃上げした中小企業には給与総額増加分の22%を減税。
・日本企業が海外に設けたペーパー会社の所得に日本の税率を適用。
・現在は相続人と被相続人が海外に5年超住んでいれば海外財産に相続税がかからないが、それを10年超に改正。
ほとんどがすでにブログでお伝えした通りの内容で、大きな変更点はありません。
「夫婦控除」などの女性の働き方改革は今後の課題という形になりました。
【所得税】配偶者控除・ビール税 与党税制協議合意
2016/12/06自民、公明両党は2日、与党税制協議会を開き、配偶者控除の見直しで一致しました。
減税になる配偶者の年収要件を現行の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げ、150万円を超えても「201万円以下」までは控除の一部を受けられる仕組みを導入するとのことです。
一方、世帯主の年収が1120万円までの世帯は控除を38万円とした上で、1120万円を超えると26万円、1170万円超は13万円と段階的に控除額を減らし、1220万円超でゼロにするにすることによって、財源を確保します。
また、ビール類の酒税は10年後の平成38年10月に一本化することで決着しました。
今回の会合で配偶者控除の件はほぼ決着となりました。
「夫婦控除」などの紆余曲折がありましたが、結局は配偶者控除の年収要件の引き上げという安易な方法を取りましたので、女性の社会進出や労働力の確保という本当の意味での問題解決には至っていません。
税以外の分野でも今後の対策が必要かと思われます。
【相続税】預貯金も遺産分割可能に
2016/12/22遺産相続の際に預貯金が遺産分割の対象になるのか争われた裁判で、最高裁は分割の対象になるとの判断を示しました。
複数の相続人が受け取り分を決める遺産分割の際、これまで不動産や株などは分割の対象でしたが、預貯金については過去の判例から全員の合意がない限り分割の対象にならず、法定相続分に従って自動的に分けられるとされてきました。
このため、一部の相続人に生前贈与がある場合などは不公平が生じるとの指摘が出ていました。
最高裁大法廷は、19日の決定で「遺産分割は相続人の間の実質的公平を図るもので、財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましい」として、預貯金も遺産分割の対象になるとの判断を示し、過去の判例を変更しました。
以前にお伝えさせていただいた内容そのままの判決となりました。
預貯金については、判例上は遺産分割の対象外とされていましたが、実務上は公平性の観点から全員の同意があれば遺産分割の対象とされてきました。
今回は実務に判決が従った形となり、より現実的で公平な取扱いができるようになりました。
【社会保険】高齢者医療保険制度 軽減特例廃止により負担増
2016/12/02厚生労働省が検討している高齢者関連の医療保険制度の見直し案の全容が28日、分かりました。
医療費の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」では、70歳以上で住民税が課税される年収約370万円未満の「一般所得者」の負担上限を引き上げるなど、負担が重くなります。
75歳以上の後期高齢者医療制度では、74歳まで扶養家族だった人の定額部分の保険料の軽減措置が、平成29年度に9割から5割に縮小されます。
さらに、現在は徴収していない所得に応じた保険料も、平成30年度から支払わなければならなくなります。
また、年金収入が153万〜211万円と比較的低い人向けに、所得に応じた保険料を5割軽減している特例は廃止となり、定額部分の保険料で8.5〜9割軽減している特例は新たに75歳になる人を含め当面存続させるようです。
政府・与党内で最終調整を進め、一部を除き来年度から実施する見込みです。
前回の介護保険に続き高齢者医療保険制度も特例廃止や軽減といった内容が目につきます。
安倍内閣は医療費削減のために大鉈を振るって改革に取り組んでいるようですので、今後も高齢者に負担を求める制度改革が新しく提案される可能性があります。
【労務】違法残業「月100時間超」から「月80時間超」へ引き下げ
2016/12/28ブラック企業をより厳しく取り締まるため、厚生労働省は26日、新たなガイドラインを発表しました。
厚労省はこれまで「月100時間超の残業を3事業所で確認した場合」に企業名を公表していましたが、新基準では「月80時間超の残業または過労死等・過労自殺等が2事業所で確認できた場合」に立ち入り調査を行い、追調査で違反が認められた場合に企業名が公表されるようになります。
電通事件を受けての厚生労働省の緊急対応となります。
これが違法残業の抑止力になれば良いですが、企業体質から変えていかないとなかなかサービス残業や隠れ残業はなくならないでしょう。
【労務】「非正規労働者に通勤費」明記
2016/12/20正社員と非正規労働者の不合理な待遇の格差をなくす「同一労働同一賃金」の実現のため、政府が作成した指針案が15日に判明しました。
通勤手当や出張旅費、食事手当、慶弔休暇は非正規を対象外とする格差を認めず、正社員と「同一の支給をしなければならない」と明記するとのことです。
それに対して、基本給やボーナスは仕事を進める能力や成果などが同じなら同水準の支給を原則とし、職業経験や成果に応じて支給内容に差を設けることも容認しました。
基本給と賞与は格差が容認されましたが、手当と福利厚生は同一に扱うべきとされました。
今回は指針レベルの規定ですので、罰則はないと思われます。
しかしながら、今後は労働基準法のように罰則が設けられることが考えられますので、パート・アルバイトを雇用されている事業主はご注意ください。
【マイナンバー】スマホ認証で本人確認
2016/12/12政府は、スマホでマイナンバーカードを読み込むことにより本人確認を行い、銀行や行政での手続きを簡単に済ませられる仕組みを導入しようとしています。
まずは来年7月に、対応するスマホにカードをかざすだけで、役所に行かなくても保育所の入所や児童手当の申請などの手続きができるサービスを、全国の自治体が導入します。
また、金融機関では群馬銀行がインターネットで送金などができるネットバンキングの本人認証にマイナンバーカードとスマホを活用することを検討しており、来年3月から実証実験を始めます。
現在マイナンバーカードの普及率が5%と言われていますので、政府としてはこの取り組みにより普及に弾みをつけたいです。
今回の仕組みは、保育所入所、児童手当申請、ネットバンキングとかなり限定的ですが、今後は免許証、健康保険証などもマイナンバーカード一枚で活用できることを目指していますので、それが実現すれば爆発的に普及する可能性があります。
ただ、スマホ認証も今のところは日本製のスマホのみですので、海外製、特にiPhoneが対象になるかが気になるところです。
お問い合わせはこちら

- 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・
- 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・
- 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・
- セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・
- 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・
お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。
 〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
☎ 075-645-1511 FAX 075-645-1512
営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)







