【岩井事務所だより】6月号「資産税関係にまつわるQ&A(譲渡所得税・相続税)」
2022/06/27
テレビや雑誌で高齢者関係の資産の話題が多いようですが、これまで以上に資産税関係(譲渡所得、相続・贈与税)の相談も増えているようです。
そこで、今回は身近な問題を取り上げ、ポイントを簡単に整理してみます。
Q 所有していた土地を5000 万円で譲渡しました。
その際、未経過固定資産税等を8 万5000 円受け取り、租税公課のマイナスとして処理しています。何か、問題はありますか。
そして、商慣習から期間按分して精算することが実務上よく行われていますが、この金額は譲渡対価としての収入金額に算入しなければなりません。
なお、補償金、取壊費用、造成負担金、測量による精算金などの名目で受け取った金額があれば、これらについても譲渡所得の収入金額とされます。
Q 令和3年中に自宅を譲渡しましたが、居住用財産を売却した場合の3000 万円控除の特例を適用したところ課税譲渡所得金額が0円(特別控除前の所得金額2800 万円)であったため、基礎控除を適用しました。
この後、問題が生じることはありますか。なお、次の諸控除については、合計所得金額に制限があるため適用に注意が必要です。
① 寡婦・ひとり親控除…500 万円以下
② 配偶者控除及び配偶者特別控除…1000 万円以下
③ 基礎控除…2500 万円以下
④ 住宅借入金等特別控除…3000 万円(令和4 年1 月1 日以後居住は2000 万円)以下である年のみ適用
その後、令和3 年に新たに自宅を取得して居住を開始し、令和3 年分の確定申告で住宅借入金等特別控除を適用して申告しましたが、問題はないでしょうか。
特に譲渡所得の特別控除と住宅借入金等特別控除は、資金の流れから関係性が深く、誤まりやすいところなので十分な注意が必要です。
新築等をした家屋を居住の用に供した個人が、下記の期間において、その家屋以外の家屋(それまで居住していた家屋など)について、居住用財産の譲渡の特例の適用を受けている又は受ける場合は、その者の居住年以後の各年分について、住宅借入金等特別控除を適用できません。
※令和2 年4 月1 日以後に譲渡した場合…その居住の用に供した年とその前2 年・後3 年の計6 年間
なお、ご質問のケースの場合、住宅借入金等特別控除の方が有利と後で気づいた場合でも特別控除を受けない修正申告はできず、住宅借入金等特別控除の適用を取り消す修正申告をすることになります。
しかし、最近になって長男が母の面倒を見ないと言い出したため、相続人間で話し合った遺産分割協議をやり直し、再配分することになりました。
このような遺産分割のやり直しは課税上問題ありませんか。
父が管理していた預金ですが、このような預金は相続財産の算定上どのように考えたら良いのでしょうか。
そして、名義を借りているだけで被相続人のものと判断されると「名義預金」として相続財産に計上する必要があります。
C さんは、周囲の勧めもあって家庭裁判所に特別縁故者への相続財産の分与請求の申立てを行っていたところ、本年4 月にその請求が認められ、相続財産の分与を受けられました。
この場合、課税関係はどうなりますか。この場合、相続税は被相続人の相続開始時の法令に基づき計算され、課税される財産の価額は、その財産分与を受けた時の価額となります。
-
 【岩井事務所だより】5月号「売上割戻しの課税関係」
岩井事務所だより5月号は「売上割戻しの課税関係」です。 事業者が取引先に対して、その仕入代金の一部を払い戻す
【岩井事務所だより】5月号「売上割戻しの課税関係」
岩井事務所だより5月号は「売上割戻しの課税関係」です。 事業者が取引先に対して、その仕入代金の一部を払い戻す
-
 【岩井事務所だより】6月号「税務面で備える 取引先にもしものことがあったら」
岩井事務所だより6月号は「税務面で備える 取引先にもしものことがあったら」です。 会社経営では、売掛金が入金
【岩井事務所だより】6月号「税務面で備える 取引先にもしものことがあったら」
岩井事務所だより6月号は「税務面で備える 取引先にもしものことがあったら」です。 会社経営では、売掛金が入金
-
 【岩井事務所だより】7月号「令和7年度税制改正 中小企業投資促進・経営強化税制の改正」
岩井事務所だより7月号は「令和7年度税制改正 中小企業投資促進・経営強化税制の改正」です。 中小企業投資促進
【岩井事務所だより】7月号「令和7年度税制改正 中小企業投資促進・経営強化税制の改正」
岩井事務所だより7月号は「令和7年度税制改正 中小企業投資促進・経営強化税制の改正」です。 中小企業投資促進
-
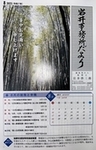 【岩井事務所だより】8月号「令和8年4月スタート 防衛増税」
岩井事務所だより8月号は「令和8年4月スタート 防衛増税」です。 令和5年度税制改正大綱の「基本的考え方等」
【岩井事務所だより】8月号「令和8年4月スタート 防衛増税」
岩井事務所だより8月号は「令和8年4月スタート 防衛増税」です。 令和5年度税制改正大綱の「基本的考え方等」
-
 【岩井事務所だより】9月号「中小企業防災・減災投資促進税制」
岩井事務所だより9月号は「中小企業防災・減災投資促進税制」です。 中小企業の、自然災害への事前対策を税制面で
【岩井事務所だより】9月号「中小企業防災・減災投資促進税制」
岩井事務所だより9月号は「中小企業防災・減災投資促進税制」です。 中小企業の、自然災害への事前対策を税制面で
お問い合わせはこちら

- 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・
- 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・
- 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・
- セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・
- 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・
お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。
 〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
☎ 075-645-1511 FAX 075-645-1512
営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)







