- ホーム
- 岩井事務所だより
- 岩井事務所だより
- 【岩井事務所だより】11月号「年末調整における定額減税」
- 岩井事務所だより
【岩井事務所だより】11月号「年末調整における定額減税」
2024/11/04
令和6 年分の年末調整では、6 月から始まった定額減税についての精算を行う必要があります。そこで、年末調整における定額減税の精算事務(年調減税事務)について取り上げます。
年末調整の対象となる人は、原則として年調減税事務の対象者になります。
ただし、年末調整の対象者のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805 万円を超えると見込まれる人は、年調減税事務の対象にはなりませんので、年調減税額(年末調整時に年調所得税額から控除する定額減税額)を控除しないで年末調整を行います。合計所得金額が1,805 万円を超えるか否かは、年末調整で提出される基礎控除申告書に記載されている合計所得金額で判定します。
定額減税額は、居住者である本人分3 万円と、居住者である同一生計配偶者及び扶養親族1 人あたり3 万円の合計額になります。同一生計配偶者や扶養親族に該当するかどうかは、原則として令和6 年12 月31 日の現況により判定します。
年末調整では、まず通常の年末調整と同じ計算を行い、住宅借入金等特別控除を適用した後の「年調所得税額」を計算します。そして、年調所得税額から年調減税額の控除を行い、定額減税額控除後の所得税額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。【図】参照
源泉徴収税額については、控除前税額から月次減税額の控除を行った後の、実際に源泉徴収した税額を給与と賞与それぞれについて集計します。
最後に、計算した年調年税額と集計した源泉徴収税額を比較し、過不足額の精算を行います。
給与所得の源泉徴収票の摘要欄には、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」と記載します。記載する金額は、年調所得税額と年調減税額のいずれか低い金額です。
年調所得税額が年調減税額より少なくて、年調減税額を控除しきれなかった金額がある場合は、その控除しきれなかった金額を「控除外額××円」と記載します。なお控除しきれない金額がない場合は、「控除外額0円」と記載します。
合計所得金額が1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)を年調減税額の計算に含めた場合は、「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6 年分の給与の収入金額が2,000 万円を超えるなどの理由で年末調整の対象とならなかった給与所得者の源泉徴収票には、摘要欄に定額減税等の内容について記載する必要はありません。源泉徴収税額の欄については、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入します。
ただし、年の中途で死亡した場合は、死亡の日の現況で判断しますので、死亡の日に扶養親族に該当するのであれば、その親族は年調減税額の計算に含めることになります。
なお、月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合は、年末調整時に精算します。
具体的には、その外国人技能実習生に居住者である同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、「源泉徴収時所得税減税控除済額0 円、控除外額30,000円」と記載します。

-
 【岩井事務所だより】12月号「令和6年分 年末調整のポイント」
岩井事務所だより12月号は「令和6年分 年末調整のポイント」です。 今年も年末調整の時期となりました。今年は
【岩井事務所だより】12月号「令和6年分 年末調整のポイント」
岩井事務所だより12月号は「令和6年分 年末調整のポイント」です。 今年も年末調整の時期となりました。今年は
-
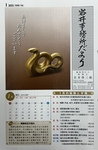 【岩井事務所だより】1月号「償却資産申告と法定調書」
岩井事務所だより1月号は「償却資産申告と法定調書」です。 1月は、法定調書や償却資産申告書などの書類の提出を
【岩井事務所だより】1月号「償却資産申告と法定調書」
岩井事務所だより1月号は「償却資産申告と法定調書」です。 1月は、法定調書や償却資産申告書などの書類の提出を
-
 【岩井事務所だより】2月号「令和6年分確定申告のポイント」
岩井事務所だより2月号は「令和6年分確定申告のポイント」です。 今年も確定申告の時期になりました。令和6 年
【岩井事務所だより】2月号「令和6年分確定申告のポイント」
岩井事務所だより2月号は「令和6年分確定申告のポイント」です。 今年も確定申告の時期になりました。令和6 年
-
 【岩井事務所だより】3月号「令和7年度税制改正(案)のポイント」
岩井事務所だより3月号は「令和7年度税制改正(案)のポイント」です。 自民党・公明党が昨年12 月に公表した
【岩井事務所だより】3月号「令和7年度税制改正(案)のポイント」
岩井事務所だより3月号は「令和7年度税制改正(案)のポイント」です。 自民党・公明党が昨年12 月に公表した
-
 【岩井事務所だより】4月号「令和6年度決算の留意点」
岩井事務所だより4月号は「令和6年度決算の留意点」です。 令和6 年4 月1 日以後に開始する事業年度から適
【岩井事務所だより】4月号「令和6年度決算の留意点」
岩井事務所だより4月号は「令和6年度決算の留意点」です。 令和6 年4 月1 日以後に開始する事業年度から適
お問い合わせはこちら

- 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・
- 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・
- 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・
- セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・
- 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・
お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。
 〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]
☎ 075-645-1511 FAX 075-645-1512
営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)







